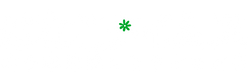このコラムは、以前「ひばりタイムス」で連載していた「書物でめぐる武蔵野」をまとめた書籍『西武池袋線でよかったね』の続編のつもりで書いている。土地と書物との境界〝散歩〟をもう一回やってみたいと思った次第だ。
手始めに、筆者の地元・東久留米市にかかわる書物から始めたい。それは、前の連載のとき筆者としては謎だったことに関係する。
▼「ドーナツ池」のモデル東久留米の厳島神社
「謎」というのはちょっと大袈裟かもしれないが、それは古田足日という児童文学者の著作に関することだった。古田は児童文学界では著名であり、個人的なことをいうと筆者の小学校時代の担任と関係があり、東久留米市に縁があることは知っていた。なので、さきほどの連載を始めるとき、この人の作品を取り上げようと思った。作品の目星もある。
おぼろげな記憶で、たしか東久留米市にある厳島神社の池をモデルにした「ドーナツ池のなんたら」というタイトルの本があるのではないかと思い、検索を続けた。しかし、『宿題ひきうけ株式会社』という遠い昔読んだ記憶があり、日本児童文学者協会賞を受賞している作品はすぐにヒットしたが、「ドーナツ池」がついた本は見当たらなかった。
「ドーナツ池」本は見つからなかったが、その厳島神社は東久留米駅から歩いて5分くらいのところに実在する。水に関係する神さまだから黒目川沿いで、いまもちょっとした森のような趣がある(上の写真)。じつは駅のすぐそばにも厳島神社がある。それと区別するためだろう、前者は神山厳島神社といわれているようだ(ただこれは今回調べてはじめて知った)。
駅そばの厳島神社の周囲はドーナツ形の池になっていて、弁天川の源流であることが『川の地図辞典 多摩東部編』(菅原健二著、之潮)によって確認できる。しかし、地元の人間にもあまり知られていないこの小さな川は、かなり前からほとんど暗渠になっていて、現在は池の水もなく、川も枯れてしまったように見える。(★下の写真)



神山厳島神社の周りもかつては水が囲っていて池になっていた。ここから北に少し行くと高い崖が連なっている(黒目川の河岸段丘)から、崖からの湧き水だったのではないだろうか。木々に囲まれ、子どもにとっては〝秘密基地〟的なたたずまいで(★冒頭の写真)、物語の舞台になるのもうなずける場所だった。ただ、これを「ドーナツ池」と称するのは、児童文学的な想像力が必要だと思う。こちらも現在は空堀のようになっていて、子どもたちが遊びにくるような雰囲気はない。
▼「学校」をはみ出す教師
さて、さきほどの連載原稿を書いたときは、やむなく古田足日氏の作品ではなく、その友人であり、彼もまた児童文学者であったことが後になってわかった、筆者の「担任の先生」小林利久氏のエピソードを書いた。それは東久留米市の戦争遺産をめぐる話だったのだが、小林先生のかなりユニークというより、現在ではありえない「教育」についてもふれた。こういう時代なので、もう少し追加する。
たとえば、授業時間に平然とクラス全員を街に連れ出し、散歩させる。60年代前半、東久留米市(当時は久留米町)は蛇行する小さな川が多く、まだ汚れていなかったのだが、その川ぞいを歩き、「ターザン」ごっこまでやらせてくれた。寺社を訪ね、戦争遺産を見たりもしたから、大義名分は「社会見学」だったのだろう。「厳島神社=ドーナツ池」にも行ったような気がする。
それは、久留米という北多摩あるいは武蔵野という東京の「田舎」だからこそなしえた教育だったにちがいない。のどかな時代だったのは間違いないが、氏に対する風圧は強くなかったのだろうか。いまの時代になってみると、そのへんの事情を知りたいと思うのだが、調べがついていない。
▼小3向け図書セット
小林先生は子どもの読書推進にも力を入れていた。小学生向けの50冊くらいの児童図書1セットを教室に持ち込み、生徒に読ませた。その図書は「世界名作文学」といったものではなく、内外の新作が中心で、そのなかに先に挙げた古田足日の『宿題ひきうけ株式会社』が入っていた記憶がある。
その児童図書のセットは「竹の子文庫」というものだった。当時、東京都教育研究所三鷹分室(通称・有三文庫=三鷹に住んでいた山本有三にちなむと思われる)という組織があり、都内各地の小中学校に、それぞれの学年にふさわしいと想定されるセットを貸し出す事業をおこなっていた。そのプロジェクトは特に小学3年生に重点を置いていた。この学年のときにうまく大人が指導すれば、かなりの読書好きになるし、そういう実績もある、と考えていたようだ。
小林先生はそれに乗り、まさに小学3年生である筆者のクラスに「竹の子文庫」が持ち込まれた。だれが一番早く全部読むかという競争もあったような気がする。読書が嫌いな子どもにとっては苦痛だっただろうが、あからさまな文句を言う者はいなかった。このとき筆者はまんまと本好きにさせられたのだと思う。
勉強は文字通り「強」いて「勉」めるものだから、小3の読書の習慣づけはありだろう。本を能動的に読むことは、たんに知識を得るだけではなく、自分で考えることにつながる。そうしないと読書は楽しくないからだ。いま世界的に、理性的な判断がないがしろになりつつある。子ども時代の読書の体験から、自分で考える習慣を身につけてほしいものだ。
ともあれ、そういう「学校」的な秩序からすこしはずれた教師だった小林利久氏は、残念なことに1991年、病気で亡くなっている。54歳だった。上記「竹の子文庫」については、死去に間に合わなかった処女作『子どもと本のふれあいをもとめて』(岩崎書店) に掲載されている代田昇氏(小林氏の文学仲間)の「あとがき」から知識を得た。
いろいろな人にとっても小林先生は「僕の好きな先生」(@忌野清志郎)であったようだ。先の記事がきっかけで、小林先生の教え子だった編集者と出会った。さらに違う編集者の弟さんも教え子であることもわかった。これは「精神のリレー」(@埴谷雄高)なのかもしれない。
▼「モグラ原っぱ」の攻防
さて、「ドーナツ池」の謎は簡単に解決した。昨年秋、民俗学者で「東北学」など地域学の第一人者である赤坂憲雄の『いくつもの武蔵野へ 郊外の記憶と物語』(岩波書店)が刊行されたのだが、そのなかに答えがあった。なんのことはない、筆者が書名を間違えていただけのことだった。
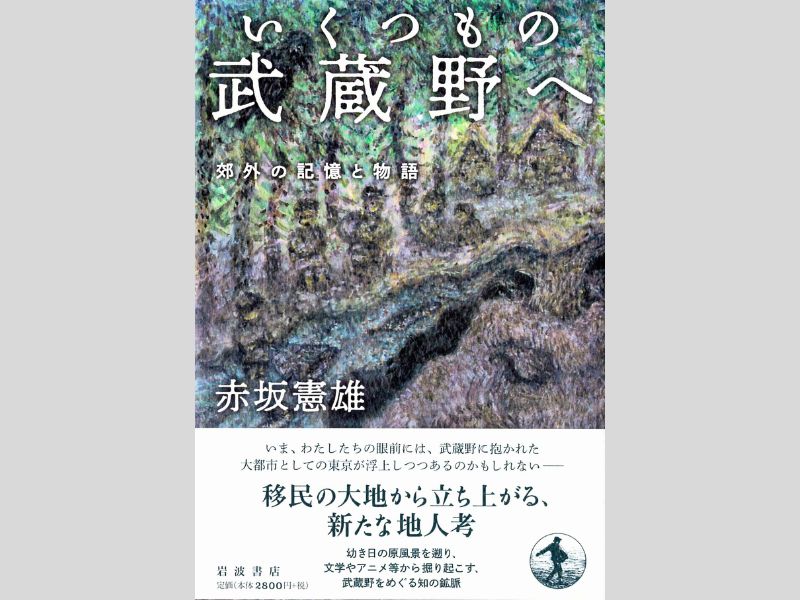
「ドーナツ池」が出てくる古田足日の作品は『モグラ原っぱのなかまたち』(1968年、あかね書房、のちに講談社文庫)というタイトルだった。この作品が『いくつもの武蔵野へ』で取り上げられていたのである。
作品の内容紹介には「その森のなかには、ドーナツ形の池があり」という記述がある。そして——、
《この作品が誕生した背景には、「まだ林や畑や泉がかなり残っていた久留米町の風土にふれた感動」があったことを、小林利久が文庫本の解説で指摘している。》p218
とある。そう、同作の文庫本の解説は小林先生なのだ。このあたりが筆者の勘違いにつながったのだと思う。
『モグラ原っぱのなかまたち』について、赤坂は、《(注:この作品は)魅力的な児童文学の一編である。物語の結末の付け方には違和感を覚えるが、そこに描かれていた雑木林と原っぱはまさしく、遊ぶ子どもたちの内なる眼が浮き彫りにする情景としてうなずけるものだ。》(p217)と評価する。
赤坂は1953年生まれ、北府中で育ったというから、高度成長期の子どもとして、原っぱや雑木林で遊んだ経験があるはずだ。だから『モグラ原っぱ…』で描かれる事柄にはリアルを感じるということだろう。しかし、結末に覚えた「違和感」とは何か。
『モグラ原っぱ…』は雑木林や空き地が残る住宅地で繰り広げられる〝子ども社会〟を描いている。その最終章は、子どもたちの遊び場の中心「モグラ原っぱ」に、市営住宅建設のため、(子どもたちにとっては)突然ダンプカーが土を運び込むところから始まる(以下、ネタバレ御免)。
子どもたちは、原っぱが破壊されることに驚き・怒り、数人が原っぱの木の上を占拠し、市長の説明を求める。親、担任、校長、市役所の職員が駆け付け大騒ぎになり、占拠は夜まで続く。やっと市長がやってきたのは夜10時だった。市長は子どもたちに住宅の中に「あそび場」を約束し、〝占拠闘争〟は終わった。
1年後、住宅地のはずれにはこぢんまりと整備された〝モグラ公園〟ができていた。闘った子どもたちは〝騙された〟感を抱き、「ほんとうの森がある世界がほしいと思いはじめていました。」という文章で物語は終わる。
しかし、「ほんとうの森」を子どもが求めるだろうか。この物語は「子どもたち」の眼に仮託された「大人の眼で再編集された」ものだと赤坂は指摘する。「違和感」はこのへんにあるのだろう。
1960年代、東京郊外は開発の波に洗われた。「武蔵野の終焉をそれと知らずに目撃した」けれども、「それ(注:開発)を懐疑したり批判する眼差しなど、移民ばかりの貧しい家族たちの群れ(注:武蔵野に住む多くの家族は地方からの移民だった)のどこにも存在しなかった」と赤坂はとどめのように書く。
にもかかわらず、この作品にはほとんど消えてしまった武蔵野の〝原風景〟が描かれている。その意味でも評価されるべきだというわけだ。
ここではいくつもの「武蔵野」をめぐる視線が交差している。高度成長期、「武蔵野」に生きる「移民」たる家族と子どもたちが見ていた、いまはない風景。それを物語化する古田の視線。その作品を読む赤坂の視線は、現在からの視線と当事者としての視線に二重化されている。それらの視線に写る「武蔵野」はどれもフェイクではない。「いくつもの」武蔵野という意味は、そういうことだと思った。
最後に筆者の私見を。たしかに本作は「子どもに仮託した大人の物語」である。この作品が書かれたのが〈1968年〉であることも無関係ではないと思うが、理不尽なことには可能な限り抵抗するという物語は、いまどきの小学3年生にぜひ読んでもらいたいと思った。

![]()