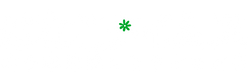「絵ごころでつながる―多磨全生園絵画の100年」展を開催中の国立ハンセン病資料館(東村山市青葉町4)で4月27日、ハンセン病患者の絵画、資料などの展示品を説明するギャラリートークが開かれ、約20人の来場客が熱心に耳を傾けた。(カバー写真)
同展覧会は国立療養所多磨全生園の前身、第一区府県立全生病院の礼拝堂で1923年に開かれた「第壱回絵画会」を起点に100年にわたる多磨全生園での患者・回復者らによる絵画活動の通史を初めてまとめた。
「絵を描くことがぼくらのすべてだ」と、厳しい隔離政策の下で絵画に魂を込め、入所者同士、入所者と職員、そして入所者と社会のつながりを求めた作品は油絵、スケッチ、園内雑誌の表紙画、日記画などに及び、いずれも見る者の心を揺さぶる。しかし残念ながら多くは失われ、作品を評した文章や写真でしのぶしかないものも多い。
戦後になって外部の美術団体から指導を受け、絵画サークル「絵の会」の中から展覧会で入選するメンバーが出るようになる。活動のピークといわれる1955年には東京都美術館で開催された「第9回旺玄会展」に9人が入選、その後も59年までに相次ぎ入選者を出した。入選作中唯一現物が残る長洲政雄の「武蔵野の森」が今回展示されている。
グループに属さず個人で活動した国吉信、望月章らのほか、極めて珍しかった女性の描き手鈴村洋子が2020年に死去するまでに残した、地蔵や祈りをモチーフとした数多くの絵はがき、障子紙の巻物などの作品も目を引く。
この日説明に当たった学芸員の吉國元さんは「この展覧会がハンセン病問題への理解を深めるきっかけとなるとともに、描き手たちのまっすぐな思いを受け止めていただければ幸い」と話している。
展覧会は今年9月1日まで。今後7回のギャラリートークや絵画教室など関連の催しが予定されている。詳しくは国立ハンセン病資料館公式サイトで。

![]()