東京・多摩地域の6市(三鷹、調布、小平、福生、東久留米、東村山)市長が地域DX(デジタルトランスフォーメーション)について語る「自治体連携シンポジウム」が1月25日、東村山市・市民センターで開かれた。
同シンポジウムは地域の枠を超えて自治体の抱える課題について意見交換しようと長友貴樹・調布市長の呼びかけで始まり、今回が13回目。各市持ち回りで開催している。
前回は2024年福生市で開かれ、地域DXをテーマとした。今回はその第2弾として、前回に続き東京都副知事で都政のデジタル化を推進する「Gov Tech東京」の代表理事・宮坂学氏が現状と今後の課題について基調講演した。
それに続いて各市長がDXに関する取り組みを説明。「LINEを使ったオンライン市役所では後発組だが、子育て世代を重点にしたところ1か月で1万人の登録を得た」(富田竜馬・東久留米市長)、「職員の意識改革、人材確保・育成、庁内の機運醸成に向けて外部人材も投入して取り組んでいる」(小林洋子・小平市長)、「市独自のデジタル通貨『アインPay』が利用者、店舗双方にメリットを発揮している」(渡部尚・東村山市長)などと紹介が続いた。
出席者による討議では、ごみの画像を撮って送ると自動で分別方法が表示され、外国人居住者にも好評だという調布市のシステムなどが参加者の注目を集めた。
また、各市がそれぞれ特性や得意分野を生かした取り組みをしているので、情報共有や協力を多摩全体にも広げていくべきではないかとの意見が出た。
次回は来年、調布市で開かれる予定。
![]()
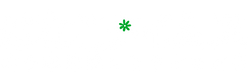

行政DXと企業DXは目的と進め方が異なる。独りよがりにならないように、広報と市民参加を工夫してほしい。
行政は防災などで上から目線で市民を教育しようとするが、デジタルは個人が先行している。行政が最も遅れていることを自覚すべきだ。
聴いていてとても物足りなく感じました。個別の取り組みばかりでDXを活用した市の全体像を語ってくれないからですね。各市長はDXの意味をわかっていない、という参加者からの発言がありましたが、私もそのように思います。東京都は支援策を用意してくれていますが、現場を知っているはずの各市にもっと頑張っていただきたいと思います。