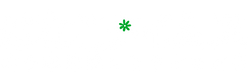東村山市議会は3月26日に閉会した定例市議会をもって速記者を廃止した。北多摩北部5市(はなこエリア)で初めてで、今後は録音音声をコンピューターで文字に変換する音声認識システムを利用して反訳を作成する。しかし誤変換などもあるため、正式の議事録として確定するためには数段階で人間による確認、修正をする。
地方自治法によって永年保持が義務付けられている地方議会の議事録作成のための速記はかつて自治体職員が担うのが主流だったが、近年では外部委託するケースが大半。さらに人材確保難や経費節減のため速記者を廃止して音声認識システム、人工知能(AI)利用も徐々に広がって精度も増している。国会ではすでに参議院で廃止、東京都議会でも2014年に廃止した。
公益社団法人日本速記協会によると、2013年現在の調査で7都道府県14人、22市区議会47人の議会職員としての速記者がいたが現在はかなり状況が変わっているとみられる。そのほかに民間速記会社に所属する速記者を議場内に配置する場合や、会議録作成に速記技能検定1級の合格者を求めている自治体がある。
同協会は「実際の発言を会議録化するには言い誤り、発音不明瞭のほか、中立性の担保などが大事な要素となる。AIの時代であっても機器に100パーセント頼れるわけではなく、必ずしも速記者でなくても必要な能力と経験を持つ者の配置が求められる」としている。
東村山市議会事務局では数年前から音声認識利用を検討してきたが人間による修正の余地がまだ多く、速記者廃止を見送ってきた。その後精度が上がったことや時代の流れを考慮して踏み切った。速記者廃止といっても音声認識などでつくった文章を、速記士を含む2重3重の人間によるチェックが必要なのは他の議会でも同様だという。
今後は録音音声を外部委託の速記会社に送り反訳原稿が戻される。それを市役所の速記士が目を通し、職員が点検を繰り返す。議事録作成までにかかる時間は速記者廃止前とそれほど変わらず、予算上削減できる費用は年間約70万円。
東村山市議会3月定例会最終日の3月26日、本会議終了後、小町明夫議長が最後となった女性速記者にねぎらいの言葉を送った。この女性は速記会社から派遣されて長年にわたり同市議会の速記を引き受けており「他にもいくつかの議会で速記をしているが、東村山市議会は明るい雰囲気で仕事がしやすかった」と議会関係者に話したという。


![]()