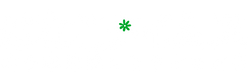介護は突然やってくる。もちろんこれは、親などの近親者が突然倒れるといったことを意味するが、突然「介護というシステム」に放り込まれる、ということも意味している。
このシステムは、一般人には耳慣れないさまざまな専門用語で運営されているので、巻き込まれる者は当惑せざるをえない。突然のことなので、受け入れるしかないのだが、経験談は他人様にも案外役に立つかもしれないと思い、筆者のケースを書いてみた(わざと個人情報を省いたところがある)。
起こったことを述べると、90代の親が腰椎圧迫骨折で入院した、というだけのことである。とはいうものの、この入院にいたるまでが、紆余曲折だった。
▼老人の腰椎圧迫骨折
「圧迫骨折」は転倒によって起こることが多いらしいが、筆者の親の場合は事情がちがった。90代の親は転倒したのではなく、ある日、腰が痛いのでシップを貼ってくれと言ったのが前兆だった。翌日事態が急変。それまでシルバーカーという歩行器を使って、炊事・洗濯からトイレまで(風呂はヘルパーの介助で)なんとか日常生活ができていたのが、腰が猛烈に痛く、ひとりでは立てない状態になった。痛みで足が動かせない。用を足すにも助けがいる。まったく身動きがとれない状態になってしまった。
もはや素人が対応できるレベルではない。かかりつけの整形外科医もいない。ただ、介護保険の「訪問看護」を利用しているので、担当のケアマネジャーに電話で相談することにした。このケアマネ、親切かつ知識が豊富、突然出現するさまざまな事態に対応できる能力をもっている。結局、この人の機転がものをいうことになった。
とにかく身動きもできず、自家用車に移乗することもできないため、ケアマネのアドバイスもあり救急車を呼ぶことにした。救急車はすぐやってきて、受け入れ先の病院も決まった。先のケアマネはなんと病院まで来てくれるという。これはケアマネの仕事の範囲外かもしれないのに、本当に有難かった。
▼「地域包括ケア病棟」という知恵
そして、病院での診断で、腰椎の圧迫骨折であることが判明した。もともとリウマチによる骨の変形もあり、転倒等の衝撃ではなく長い間の圧迫で骨折にいたったようである。
そのように診断した病院の担当整形外科医は、われわれ患者とその家族に次のように語った。
圧迫骨折で入院できるのは、手術の必要がある場合のみ。筆者の親のように、高齢ということもあって手術しない(できない)人は自宅で療養となる、「社会的入院」はできない、ということである。
筆者は「社会的入院」という言葉を知らなかった。介護は突然やってくるというのは、このように突然、専門用語の世界に放り込まれることなのである。
あとで調べてわかったのは、「社会的入院」というのは、「入院による治療の必要性が低いのに、いろいろな理由で入院の続く状態」をいうらしいこと(「デジタル大辞泉」を参照)。この病院の整形外科医は、痛みを訴え、身動きのできない筆者の親の状態を「入院による治療の必要性が低い」と判断したようだ。
病床数の不足、介護・医療保険などの面から入院が社会的な問題になっているのはわかるが、素人では対処のしようがないから救急車でやってきたわけで、自宅に帰るなどとうてい承服できない。途方に暮れかけたところ、同席してくれたケアマネが助け船を出してくれた。専門知識を使い、反論してくれたのである。
「こちらの病院には地域包括ケア病棟があるわけですから、そこに入院させてほしい」
これは有効だった。話し合いの結果、その病院の「地域包括ケア病棟」に入院することができた。
「地域包括ケア病棟」というのは、「急性期の治療を終えた患者や、自宅や施設で療養中に緊急の入院が必要になった患者、直ぐに在宅や施設へ移行するには不安のある患者に対して、治療と共に在宅復帰に向けて支援したり準備したりする病棟」(地域包括ケア推進病棟協会HPより)で、筆者の親は「直ぐに在宅へ移行するには不安のある患者」に該当すると医者も判断したのだろう。ケアマネの経験と知恵がなければ、筆者の親は自宅に帰されたのだろうか、想像するだにおそろしい。
じつを言えば、この事態をケアマネは読んでいて、救急車に搬送先の希望を言う際、「地域包括ケア病棟」のあるいくつかの病院を希望するように入れ知恵されていたのだった。
▼教訓
このように、筆者はひじょうにラッキーだったといえる。何度も書くがこのように「越境的」な面倒をみてくれるケアマネが担当だったのが幸いしている。
介護の世界は「専門用語」でいっぱいなので、一般の人間はとまどう。ケアマネジャー=介護支援専門員に、その「専門性」を発揮してもらえるよう、利用する者もうまく付き合う必要がある。わからないことは、どんどん聞いたほうがいい。メモも有効だった。


![]()