鉄道の駅やバス停留所から離れた地域に住み、自家用車などの移動手段を持たない高齢者、障害者、幼い子ども連れなどのいわゆる「交通弱者」に向けた公共交通サービスとして、東村山市が約半年にわたって行っていたタクシーを活用した予約型乗合交通の実験運行が2025年6月、終了した。
対象は市内在住者で、利用を希望する人は事前に登録し、実際に利用する2週間前から24時間前までに原則ネットで予約。市内の公共交通空白地域と認定された6つのエリア内に指定された計58の乗降場からエリア内の鉄道駅やバス停まで市が契約したタクシーが運送する。平日のみ運行で、運賃は大人1人につき1回500円。予約が重なった場合は相乗りとなる。
東村山市によると、期間中利用登録したのは326人、乗車人数は延べ300人で1日平均2.73人だった。これは実験運行から実証段階に進むための条件とされた1日当たり33人の10分の1にも満たず、あらためて実験を行う方向で検討するという。
同市が実施したアンケートには「土日の運行や運行時間延長を」「エリアをまたいで医療機関や市役所で乗降したい」などの要望が強く、今回の登録者、未登録者とも大半が今後は利用したいとの意向を示した。以上の結果を踏まえ、より利用しやすくするよう改善を図る。
予約型でタクシーを活用した公共交通はオンデマンド型とも呼ばれ、北多摩北部(はなこエリア)各市でもさまざまな取り組みが進められている。地域公共交通としてはコミュニティバスが普及しているが、基本的に定時、定路線の運行で、マイクロバス型を利用するため、ある程度の幅員確保をはじめ道路整備が条件となる。
5市中面積最大の小平市では停留所設置、定時・定路線のコミュニティタクシー「ぶるべー号」を運行しているが、市南西部地域を対象としたデマンド型の乗合タクシー実証実験を2024年6月から2025年5月まで実施、結果を分析中だ。
西東京市でも5路線で運行中のコミュニティバス「はなバス」とは別の新たな移動支援の実証実験を2019年6月に始めたが、コロナ禍などのため約3カ月で打ち切りとなり、2025年10月から2027年3月にかけてあらためて同市南部地域でミニバンサイズのタクシーを利用して実証実験を行うことにしている。
東久留米市は市内の道路状況などからコミュニティバスを運行しておらず、10人乗りワゴンタイプのデマンド型交通「くるぶー」を、5年間の実証実験を経て2025年4月から本格運行している。事前登録し、オンラインで24時間予約可能。1人1回500円で共通乗降場34カ所から利用可能だ。
清瀬市はコミュニティバス「きよバス」を運行中で、それ以外の移動手段については今のところ考えていないという。


![]()
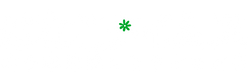

オンデマンド型にしても、定期便にしても、自治体の目標設定値が高すぎると思います。単一の行政区域での運用も利用者のニーズに合っていると思えません。鉄道、路線バスを含めて、近隣の自治体が協力して、住民の生活を支援するインフラである、公共交通を運用していただきたいです。