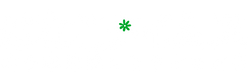こどもの権利に対する理解を深め、こどもの意見表明や社会参画を進めようと、東村山市が主催する「こどもの権利シンポジウム」が8月2日、東村山駅西口サンパルネで開かれた。こどもや若者に関する活動を展開するパネラーがそれぞれの立場から報告や意見交換を行い、会場の約100人が熱心に耳を傾けた。
シンポジウムでのあいさつに立った渡部尚・東村山市長は2025年4月にスタートした「東村山市こども計画」について説明した。これまでのこども・若者に関する諸施策をまとめ「こども・若者一人一人が主人公 みんながつかむ笑顔のミライ」を基本理念とした。その上で「権利の保障、侵害の防止」「健やかな成長応援」「支援必要なこども・若者に寄り添う」「成長を支える環境づくり」の4つを基本目標に、具体的に取り組むという。
静岡県を中心にこども・若者の社会参画、意見反映に取り組むNPO法人わかもののまち代表理事の土肥潤也氏が基調講演。それによると、こども基本法が2023年に施行されて以来、こどもをめぐる施策と考え方は大きく変わった。こども・若者に関する政策決定に当たって、当事者としてのこども・若者の意見を聞くことは義務になりつつある。
土肥氏はさらに、こどもはこれまで保護の対象だったが権利の主体であり、「こども優先」ではなくこどもと共に考えることが必要となる。こうした国の政策転換は国際的にはむしろ遅れていた。自治体もこれに合わせた転換が求められており、東村山市は課題を網羅的にとらえた計画をつくり、こども向けの説明書も用意するなど一歩進んでいる。こどもの声の聴き方を工夫し、反映させる努力も重要だ―などと報告した。
続いて行われたパネルディスカッションには、白梅学園大・大学院教授の仲本美央氏、東村山eスポーツ振興・推進団体「とんぼ会」会長の大草翔太氏、東村山市民生委員・児童委員協議会主任児童委員部会長の竹田陽子氏の3人が登壇、土肥氏と共に議論を進めた。
仲本氏は「幼いこどもも自らの意思、意欲を持っており、大人が耳を傾け、共感しながら一緒に考える姿勢が大事。遊びを通じてこどもが多くを教えてくれ、学びになっていくことがある」と研究、実践を踏まえながら指摘した。
大草氏は「ゲームを通じてこどもたちのつながりをつくる活動をしている。こどもの意欲や希望をどう具現化していくのかをサポートする場をもっと広げたい」と述べた。
竹田氏は「地域の日常をよく知り、身近な相談役として存在し、パイプ役としての機能を果たす」と民生委員の経験を通じて得た基本原則を紹介しながら、地域に根差した緩やかでさりげない支援の大切さを訴えた。
シンポジウムを聴いたある市民は「こどもの権利侵害の最たる姿は虐待、貧困、いじめ、そして自殺に至るような耐え難い現状だ。これをどう防止し、救済するのかという喫緊の課題について具体的にはほとんど触れられなかったのは残念だった」と感想を話した。


![]()