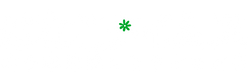『団地のふたり』が、11月3日(日、NHKのBS午後10時)で最終回(10回目)となった。原作も続編にあたる『また団地のふたり』(藤野千夜、U-NEXT)が刊行された。本サイトとの関連でいうと、NHKはクレジットしてはいないが、明らかにロケ地は東久留米市の滝山団地である。そしておそらくこのドラマはかなり人気があった。〝団ふた〟ロス (と呼ばれているかわからないが) をちょっとだけ埋めるかもしれない一文を草してみた。ネタバレ御免。
・先に読みたい:【北多摩駅前物語】ドラマ『団地のふたり』には、いきなり花小金井駅南口が出てきた
▼予想がはずれた
最終回の1回前と最終回の予告を見て、これは小林聡美と小泉今日子が共演している約20年前のドラマ『すいか』パターンだと早合点した。前にもこのコラムで書いたが、『すいか』もまた日常性を描いたドラマで、小さな下宿に住まう人びとの〝いい話〟で構成されていた。
・あわせて読みたい:【コラム】『団地のふたり』の周辺をめぐって
しかし、幸せの時間は長続きしないというのは世の常。「この関係がこのまま続けばいいのに」と当事者もドラマの観客も思っていても、それはかなわない。これは、ひとつのドラマ作法だと思う。『すいか』はその線だった。
『団地のふたり』も、さびしいけれど、別れたくないのにお別れ、涙涙の最終回かと思いきや、最終回の冒頭でいきなり「ちゃぶ台返し」された(筆者がだまされやすいのかもしれないが)。
舞台となっている「夕日野団地」は、駅から遠い郊外の立地で、知名度もなく、建て替えても新しい住民が入りそうにない、という理由で開発業者が撤退し、建て替え話はご破算になった。なので、団地のみんなは出ていく必要がなくなったのである。
時は2025年、つまり来年=未来のことになるが、みんなバラバラになるどころか、一度団地を出ていった佐久間のおばちゃん(由紀さおり)や福田さん(名取裕子)も戻ってきた。おまけに、主人公たちが仲良くする団地在住の女子小学生がSNSで配信する動画がバズりはじめる。近所の昭和的な喫茶店には行列ができ、「動画を見ているとほっこりする」、「癒しの団地」だとか、「この団地に住みたい」というコメントが寄せられ、団地はある種の憧れの場所になっていた。
つまり、動画への評価がこのドラマの評価にもなっている。団地はみんなが帰ってこられるふるさとであり、スイートホームであり、ちょっとした理想郷であることをあからさまに言わない、なかなか味のある描かれ方になっていた。これは、『団地のふたり』にふさわしい最終回だったといえるだろう。
出てくる人はみんないい人、クレマーで嫌なオヤジでさえ根はいい人だった、なんていうのはきれいごとだし、ドラマのなかでしか成り立たないことは、見る側はわかっている。にもかかわらず、そういう虚構を求める社会的な無意識のようなものが広がりつつあるのだろうか。
このドラマでは、古臭さが一巡してレトロで安心できる「良さ」に変わっていた。団地そのものがそうだし、家族をはじめ人間関係はギスギスしない〝ご近所〟が成り立っているようにみえた。異邦人を意図的に組み込んだのは、今日的な演出だろう(これから排外主義が進む世界になっていくかもしれないのでこれは大切)。
ただこういう理屈は、かえってドラマをつまらなくするかもしれない。そういうことより、夕陽がきれいだったり、ホットケーキが美味しかったりすることを日常の小さなシアワセと感じさせるドラマが、うまい具合に成立していたということだ。
どこかとぼけた味わいのテーマ曲や劇伴の音楽も効果的だった。昭和歌謡づくしのふたり紅白歌合戦は、どういう年齢層を狙ったドラマなのかを如実にあらわしていた。最後にふたりで歌う「蛍の光」は、これまた「入れ子」構造になっていて(紅白ごっこの終わりとドラマの終わり)、「ああ、終わってしまうんだ」としみじみ感じさせてくれたのだった。
でも、団地はいつか建て替えなくてはならないはずだけど……。
▼ヴィム・ヴェンダース『パーフェクト・デイズ』
こうした日常を描いただけなのに、ドラマを感じさせてくれた最近の印象的な作品に、ヴィム・ヴェンダース監督、役所広司主演の『パーフェクト・デイズ』がある。去年の公開、同年のカンヌ国際映画祭で、役所が男優賞を受賞したことで話題になった。
ヴェンダースといえば『ベルリン天使の詩』(87年、カンヌ国際映画祭最優秀監督賞)である。公開当時「ニューアカ」ブームなどがあって、知的にもバブルだった日本の状況では、これを知らないとは口にできないような作品だった。『ベルリン…』も、いわゆるストーリー展開重視の作品ではない。ヴェンダースは小津安二郎を敬愛していると聞いていたから、『パーフェクト・デイズ』は知的なのはわかるが、眠くなると困るなと危惧していた。
だが、それは杞憂だった。役所広司演ずる主人公が、毎朝きちんきちんと起き、軽自動車に乗ってルー・リードほか古いロックのカセットテープを聴きながら、渋谷の公衆トイレ(さすがにデザイン化されたキレイなトイレ)を回って丁寧に掃除する。昼休みには神社に行って弁当を食べ、頭上の樹木を撮影し、銭湯に行き、浅草の安食堂(NHKのドキュメント72時間に登場したことのある店)で夕食を食べ、石川さゆり演ずる女将がいる店でときどき一杯やり、帰ってからは古本屋で仕入れた小説の文庫本を読んで寝る。このルーティンがじつにいいのである。
映像が詩的なのは大きい。挟み込まれる古い音楽も効いている。映画タイトルの『パーフェクト・デイズ』はルー・リードの「パーフェクト・デイ」に由来すると思われる(DaysとDayの違いに注目を)。ここに役所の力量が加わって、日常の描写がこころにしみるドラマとなった。『団地のふたり』もそうだが、日常を描く作品には、役者の力量がどうしても必要になる。
『団地のふたり』は、時代からちょっとはずれているがゆえに、ゆるくも温かい人間関係や地域の共同性への漠然とした憧れが生まれ、これを背景にした日常性をドラマ化させた。
一方、『パーフェクト・デイズ』は、人間は生きているだけで価値がある、いやむしろ、生まれて、生きて、死ぬ過程こそ価値の源泉であることを示している気がする。つまり、名士になろうがホームレスになろうが、どんな生き方をしようともひとの価値は同じである。
そうではない、と考えるのが世間というものだ。だから職業をはじめとしたさまざまなことについての蔑視、差別がなくならない。蔑視とはいわないまでも、『パーフェクト・デイズ』の主人公とその妹(麻生祐未)の価値観は違う。
これに対抗するには、蔑視を成り立たせている価値観より広く長いスパンの視線を手に入れることだろう。そうすることによって自分が生きていることに矜持をもち、自分の価値観を貫くしかない。
しかし、それは思ったように運ばない。だから、それがドラマになる。

▼竹内まりやの『プレシャス・デイズ』
この『パーフェクト・デイズ』を、きっと意識しているに違いないと思った作品がある。10月に発売された竹内まりやの新作アルバム『プレシャス・デイズ』である。「デイズDays」が同じだけじゃないかというなかれ。この方、今回のアルバムを売るために、かなりのプロモーション活動をしていて、めったに出ないテレビにも2回出ていた。その際、「日常を大切にしたいがゆえにPrecious Day大事な日ではなくPrecious Days大事な日々にした」というようなコメントをしていた。
これはまったくの私見だが、このDaysは間違いなくつながっていると思う。
竹内の楽曲世界は、『VARIETY』というアルバムもあるくらいバラエティに富んでいる。
多数の不倫ソングがあり、都市を生きる女性の虚無感を描いた「プラスティック・ラヴ」など世界にシティポップ・ブームを起こすきっかけになった楽曲も印象深いが、日常の一瞬のきらめきを大切にしようとする一連の作品がある。ずばり「毎日がスペシャル」という曲があるし、「どんなちいさなことも覚えていたい」とうたったりしている(「人生の扉」)。
彼女の恋の歌が、短編小説の一シーンのようなフィクションであるのと同じように、日常のきらめきもフィクションかもしれない。なにしろ、ふたりの男に〝私のために争わないで〟とうたう「けんかをやめて」を、〝何様ソング〟と本人が呼んでいたくらいだから、指摘されたりすると、日常性も絵空事と言いかねない、とは思う。
にもかかわらず、竹内の楽曲だったり、『パーフェクト・デイズ』や『団地のふたり』が描く日常は、虚構なのはわかっちゃいるけどPreciousだ (愛おしい)と思う。

最後になったが、『団地のふたり』の原作小説の続編、藤野千夜『また団地のふたり』について。本作をいま読むと、たとえていうと、味付けの濃いものを食べた後に、薄味の料理を出された感じになってしまうかもしれない。あまりにドラマの小泉今日子と小林聡美のキャラが強すぎて、「なっちゃん」と「ノエチ」が自立してくれないのである。ドラマとはまったく違うエピソードがつづられているのでもったいない。もう少し時間が経ってから読んだほうがいいと思う。

![]()