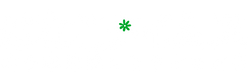2022年の北京冬季オリンピック。このとき北京とともに開催都市となった「張家口(ツァンチァコウ)」という地名を聞いたとき、ひばりヶ丘駅南口にあった碁会所とその席亭である横田都志三さんを久しぶりに思い出した。張家口、懐かしい地名である。私は訪れたことはないのだが。
◾️「ひばりが丘囲碁センター」
私が高校を卒業した1978年に「ひばりが丘囲碁センター」は開業した。ひばりが丘駅南口を出て今のパルコの前の道を南下して安田信託銀行先の右側ビル3階だった。1階はサンドウィッチ店、2階は消費者金融の武富士、向かいには宮園書店という本屋があった。ここは日本棋院にも申請して「日本棋院ひばりが丘支部」も兼ねた。
そこのオーナー席亭が横田さんだった。当時、私はアマ初段くらい(プロとアマの段位は全く別のもの。以下はアマ段位)で横田さんも同じくらいの棋力だった。何度か打ったことがある。記憶ではこの頃はひばりが丘駅周辺には北口側も含めて確か4軒の碁会所があり、一通り顔を出すことになるのだが、新しくてきれいで雰囲気もよく、席亭の穏やかな人柄も気に入って1991年まで13年間に渡って通うことになる。ここで碁打ち仲間もできて、呑みに行ったりバーベキューに行ったりと囲碁以外でも遊んだりするようにもなった。

私は囲碁を小学校6年生の頃に父に教えられてハマッてしまい、中学3年間の部活動は囲碁クラブに入った。幸運にも顧問の先生が四段で、なぜか私は見込まれたらしく部活動日以外でも放課後に打ってくれた。卒業時には、「初段でいいだろう」と認めていただけた。ずっと級位者だったのが、有段者と名乗れるのが嬉しかった。
高校に囲碁部はなかったが囲碁への熱は醒めず、新聞の囲碁欄を並べたり日曜日昼放送のNHK杯囲碁トーナメントを見たりはしていた。しかしこの3年間は実戦経験のないブランクで、棋力は停滞していたと思う。
この間に、街には「碁会所」というものがあって、一人で行って自由に打てる、昔で言えば他流試合ができる、ということを知った。これも幸いにも、ちょうど高校を卒業した年に上記したように地元ひばりが丘に碁会所ができて、そこに恐る恐る行ってみたのだった。何せ高校を卒業したばかりで、そういうところに一人で足を踏み入れるだけでも勇気がいった。ただ、特殊な人は別にして、囲碁は麻雀のように賭けることはない、と聞いていたので、知らない人と打ってみたい気持ちが勝った。囲碁は賭けなくても充分に楽しい。第1級のゲームだと思う。
◾️碁会所のシステム
碁会所というのは、グループで行ったりするよりは1人でふらっと訪れるのが普通で、席亭(店主・支配人)が相手をつけてくれる。初回は、自分の棋力を自己申告すればよく、私の場合は確か、初段くらい、と告げたと思う。そうすると、大体、2級~三段くらいの相手をつけてくれる。手合い割(ハンディの有無)も席亭が決める。自分の棋力が分からなくて自己申告できないような場合には席亭が自ら対局して把握することもある。
このようにお客さんの棋力を把握して組み合わせを決めなければならないし、お客さんが少なくて相手を組めないときには対局相手を務めることもあるので、席亭にもある程度の棋力は必要である。県代表クラスの人は自ら指導碁を打ったり、教室を開催したりしている人もいる。
この席亭の人柄と客層によって雰囲気が決まり、その雰囲気との相性で行き先が決まることが多い。私は「ひばりが丘囲碁センター」の空気が多分合い、定着したのだろう。毎回のように行き先を変える人はあまりいないと思う。サラリーマンは職場近くと自宅近くに行きつけを持っている人が多かった。行きつけになると、多い人は毎日、少ない人でも週に1回は訪れる。
お客さんはさまざまで、とくかく多く打てればいいという人、格下と対局するのが好きで格下でもなんでも勝ちさえすれば嬉しいという人、反対に対局数は少なくても丁寧に打って棋力向上を図りたい、つまり強くなりたいという人、といろいろいる。超早打ちの人もいれば、長考派で一手一手にじっくり考える人もいる。だから組み合わせによっては、一局が20分足らずで終わってしまったり、逆に2時間以上うんうん唸りながら打っていたりもする。年齢・職業・性別・棋力の違いはもちろんだが、こういった気持ちも志も対局態度(マナー)も雑多な人たちが、対局という勝負の世界でつながっているのが碁会所である。
私は棋力向上の気持ちが強かった。だから、雑に打ってくる人は好きではなかった。そういう相手には必ず勝たなければいけない、という思いで打っていた。碁会所には規定があって、所定の成績を上げれば昇段できる。それが励みになる。
◾️直接向き合って対局するということ
こうして、初対面、未知の人と対局することから始まるが、通うにつれて同じ人との対局も増えていって、顔や名前や職業などプロフィールもだんだんわかってくる。特に囲碁の場合は局後の検討をおこなうことが多いのが大きいかもしれない。初対面でも終局後に感想を述べあって、ああでもないこうでもない、と石を並べ直しながら変化を検討し、対局を振り返って勝因・敗因を分析する。だから、そこには勝負の敵・味方でありながら研究仲間のような関係も生まれてきて、ある意味同志である。そうやって、上記したように碁会所以外の関係が生まれることも多く、帰りに呑みにいくようになるなどはよくある光景である。呑めばさらに親しくなる。
この直接向き合って対局するというのが重要で、これが碁会所文化を作ってきたのだと思う。少子高齢化の流れで囲碁人口が減ってきているところにコロナ禍は決定的で、この間に多くの碁会所が廃業に追い込まれた。外出するな、人に会うな、という規制の中では碁会所に足を運ぶのも躊躇した人が多かっただろう。
インターネットが普及したこともあってネットで碁を打つ人が増えてきていたが、コロナ禍でネット碁に流れてしまった人も多い。コロナ禍が明けても碁会所に戻ってくる人は少なくて碁会所の苦境は続いている。特に高齢者は外出が億劫になってネット碁のみ、でなければ碁をやめてしまった人も多いと聞く。ネット碁は好きなときに好きな相手を選んで打て、名前はハンドルネームでよく、プロ棋士や全国レベルのアマも参加していると聞くが、私はネット碁はやらない。やはり、相手の表情や息遣いなどが感じられないし、クリックしてモニターの碁盤に石を表示するのでは碁を打っている気がしない。

◾️席亭は満洲引揚者だった
通って慣れてきた頃、この横田さんが中国からの引き揚げ者であることを知った。張家口にいたのだという。そして、その引き揚げの記録を出版したということが分かって、本人から直接買って読んだ。サインもしてもらった。その本は《横田都志三著『思い出は張家口の彼方に 張家口引揚げの記録』》(後楽出版、1983年)である。
ひばりが丘に住んでいた横田さんは、1913年11月28日生まれ。生家は埼玉県比企郡川島村(今の川島町)の農家で、早稲田大学専門部を卒業して親和貿易株式会社に就職した。親和貿易は満洲・朝鮮との貿易をしている会社だったが、満洲で事業を起こして国に尽くしたいとの思いが募って、曲折はあったが内蒙古にあった大同炭鉱株式会社に勤めることになり、張家口に住んだ。だから動員や開拓団ではなく、いわゆる「一旗組」に近かったようだ。敗戦になって、横田さん夫妻は天津の外港である塘沽(タンクー)港から辰日丸で1945年11月6日に博多港上陸を果たしたのだった。天津で発行された引揚げ証明書の写真も掲載されている(同書、p.87)。
この碁会所のお客さんに橋本哲男さんという毎日新聞を定年退職した記者がいて、この人に勧められてこの記録を書いた。出版も橋本さんが世話したらしい。巻末に橋本さんが「横田都志三さんのこと」という小文を書いている。この橋本さんは三段くらいで、やはり何度か打ったことがある。なお、横田都志三著となっているが、半分くらいは奥さんである故・林(りん)さんの日記が占める。戦後の生活記録で、病気で亡くなってしまったこの奥さんの日記を何とか出版したいというのも横田さんの執筆動機にはあったようだ。
わが師匠(と私は勝手に言っている)であるIさんもこの碁会所に師範として来ていて、指導碁を打っていた。後にIさんもこのひばりが丘に碁会所「幻庵」を開業するが、対局仲間も多かったのでやはり「ひばりが丘囲碁センター」に行くことが多く、私が「幻庵」に通うようになるのは横田さん没後の1992年からである。その頃、私は五段くらいになっていた。この碁会所で成長させてもらったわけである。

◾️「幻庵」という碁会所もあった
「幻庵」は「ひばりが丘囲碁センター」をさらに南に進んで、ひばりが丘団地方面に行くバス通り沿い、MIC(社会調査研究所、現在インテージ)の向かい側の建物の2階にあった。1階は居酒屋だった。席亭のIさんは大学囲碁部出身、全国クラスの打ち手だった。私はここでもIさんに見込まれたようで、行けば必ずIさんが打ってくれ、更にレベルを引き上げてくれた。今ではどこの碁会所に行っても高いレベルで打てるようになった。だからIさんが師匠だ。
「ひばりが丘囲碁センター」は、横田さんが亡くなった後、再婚後の奥さんが引き継いでやっていたが、しばらくして廃業した。「幻庵」も、後に自宅を改築してその2階に移転したが、今はない(Iさんは健在である、念のため)。
そもそも碁会所は商売としては儲からないだろう。席料は、私が通い始めた当時で500円くらい、今でも800~1500円程度が普通である。それで開店から閉店まで終日打てるのである。昼食などで途中外出しても追加料金はない。雀荘のように滞在時間やゲーム数で加算されていくこともない。席亭は皆碁が好きでやっているのである。Iさんは「幻庵」を主宰する傍ら、囲碁ライターとして囲碁雑誌などに観戦紀や囲碁講座を執筆していた。
もともと利の薄いところに加えて、コロナ禍で来店するお客さんが激減した。サークルに入るなどしないと直接顔をあわせて対局することは難しくなってしまった。私は大学では囲碁部に入らなかったので、いわゆる碁会所派である。大学囲碁部出身者からは、囲碁部出身者でなくてこのレベルまできたことに驚かれることが多い。その私も、碁会所には行っても今や仲間と作っている研究会とプロ棋士に受ける指導碁での対局が主になってしまった。碁会所文化は風前の灯である。

あわせて読みたい:
・【北多摩駅前物語】保谷駅北口「山田うどん」目指して駆ける
・【北多摩駅前物語】小平編 KEY COFFEE
・【北多摩駅前物語】保谷駅南口編 神技バスはもう見られない
・【北多摩駅前物語】ひばりヶ丘 開業100周年イベントでよみがえるそれぞれの記憶
・【北多摩駅前物語】高校で習った『おわい電車』の思い出と清瀬
・【北多摩駅前物語】「ひばりヶ丘 北口編」62年前のひばりヶ丘駅北口は、ここだった
・【北多摩駅前物語】ひばりヶ丘 南口編 開業100年を迎えたひばりヶ丘、62年前の駅前風景
![]()