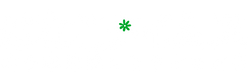詩人・谷川俊太郎さんの訃報が届いた。御年92歳だったという。心からご冥福をお祈りしたい。
谷川さんと私の接点はほぼないのだが、今はもうなくなってしまった私の母校「田無市立西原小学校」(のちに西東京市立)を通じて、少しだけ存在する。その学校の校歌は「作詞:谷川俊太郎」であったのだ。
教室は宇宙船 どこへだってゆける
けやきのこずえに つづくあおぞら
大きなゆめをもとう 西原のぼくとわたし
という校歌は、人生初めて歌った校歌だったし、以後の人生の中でも最高の校歌だったと思う。谷川氏らしいスケールの大きさと児童たちへのメッセージ。小さいころから知っている詩だが、今読むとまた違う気持ちにさせられる。
この西原小学校、実は西原町ではなく芝久保町にあった。西原団地の子供のために作られた学校なので、この名前が付いたのだと思う。
近隣にさらに新しい団地ができるなど児童が増加したため1980年(昭和55年)に西原第二小学校ができて、西原小の学区域は二つに分離された。そしてその後の児童数の減少により2001年(平成13年)に西原第二小学校(こちらは西原町にあった)との統廃合で名前が変わり、けやき小学校となる。
けやき小は西原小と同じ敷地にあるのだが、なぜ名前を変えてしまったのか。おそらく所在地が西原町でないことが大きな理由だったのだと思うのだが、校名の変更によりこのスケールの大きな校歌まで廃止になってしまった。この歌をもう子供たちが歌うことがなくなってしまったのは、誠に残念なことである。
さて、西原小学校の最寄り駅は花小金井駅であった。遠足のときは1学年200人ほどの小学生が、15分ほどかけて、車通りの多い細い道を花小金井駅まで歩いたものだ。
当時の花小金井駅は田舎の駅そのもので、改札は北口しかなく、改札を入ると踏切を渡ってホームに登っていくスタイルだったと記憶している。もっとも調べてみると、団体客のみ踏切を渡るようになっていたという説もある。
ホームそのものの位置は現在と変わらないが、田無駅のような、2本のホームに3本の線路がある形(2面3線)だった。そして、小平方向は行き止まりになっており、新宿方面から来た電車が中線に入ると、それ以上進めない構造だったようだ。のちに中線が埋められて、現在のような太いホームになった。
駅前広場も全くなく、道も、現在の広場の一つ東側の細い道が、北側から駅にアクセスする道路だった。その細い道を、西原小の小学生たちはみんなで歩いたのだった。
当時駅の北側には拓殖大学第一高等学校があった。このアクセスが良い、駅前の高校に通う生徒たちは、どのような花小金井ライフを送っていたのだろう。その高校も駅前再開発の影響からか、2004年(平成16年)に武蔵村山市に引っ越してしまった。
花小金井は、今とは比較にならないくらい、のどかな駅だったのだ。

あわせて読みたい:
・【北多摩駅前物語】ドラマ『団地のふたり』には、いきなり花小金井駅南口が出てきた
・【北多摩駅前物語】ひばりが丘には碁会所文化があった
・【北多摩駅前物語】保谷駅北口「山田うどん」目指して駆ける
・【北多摩駅前物語】小平編 KEY COFFEE
・【北多摩駅前物語】保谷駅南口編 神技バスはもう見られない
・【北多摩駅前物語】ひばりヶ丘 開業100周年イベントでよみがえるそれぞれの記憶
・【北多摩駅前物語】高校で習った『おわい電車』の思い出と清瀬
・【北多摩駅前物語】「ひばりヶ丘 北口編」62年前のひばりヶ丘駅北口は、ここだった
・【北多摩駅前物語】ひばりヶ丘 南口編 開業100年を迎えたひばりヶ丘、62年前の駅前風景
![]()